羽越本線の車窓から見た旧坂町機関区の給水塔。近くに転車台もあるのだが分かりづらかった。この転車台は現代もSL運行時に使われるらしい。
坂町駅
新潟県村上市坂町
1914年(大正3年)11月1日開業
八王子 高尾 木蓮 開花状況
同じく高尾にある大光寺の桜は3日ほど前にライトアップしていたが、高楽寺の枝垂れ桜はライトアップしていなかった。まだ見頃ではないのか、それとも20時過ぎは照明を消してしまうのか、不明。木蓮の花はもう花弁が散り始めていた。
高楽寺 – Wikipedia
〒193-0941 東京都八王子市狭間町1868
北海道立 北方民族博物館公式サイト(網走)を見学。館内で流していたクマ送りの儀式の映像にとても惹かれた。あと本場オホーツクの人々の口琴の映像も良かった。
〒093-0042 北海道網走市潮見309−1
熊送り儀礼に使われる打楽器 北方民族博物館の館内映像(撮影自由)
ウリチ/アムール川下流域 Ul’chi/Lower Amur
熊送り
熊を獣のなかで特別な存在とみなし、これを殺害するときに執行される儀礼の総称。この儀礼は、北方ユーラシア大陸を中心に、北アメリカ、ベトナム山地、バスク地方など、熊の生息する地域のほとんどの民族にみられ、俗に熊祭といわれることもあり、アイヌではイオマンテという。つまり、熊のすむ地帯では、他の獣を超えた力をもっていることから、熊は獣の王、野獣世界の支配者とみなされる。また、人間が森の中で遭遇するもっとも危険な存在であることなどから、森の主にも位置づけられる。この森と人間の村とが一つの宇宙を形成しており、儀礼の対象となる熊は、森の野獣世界から人間社会を訪問し、そこで手厚い歓待を受け、丁重な儀礼をもって殺害される。これによって初めて毛皮や肉などの仮装を脱ぐことができ、そして神のいる森へふたたび帰るために不可欠な霊的存在になることができるとされる。
熊送り(熊祭)|日本大百科全書・世界大百科事典|ジャパンナレッジ
この映像を見た時、何とも言えない恐怖と畏怖と神聖さを感じた。私は無宗教なのに何か軽々しく立ち入ってはいけない領域のような気がした。以前は「生贄」というと残酷な風習のように感じていたが、熊送りの映像を見た時「生贄は必ずしも残酷とは言えないのでないか」と感じた。もちろん犠牲になる熊にとっては残酷な行為だけれども。恐らく昔の人は熊を殺す時に命の重みを感じて儀式に臨んだのでないか。現代では考えられないような不条理な習慣もあっただろう。とてつもなく恐ろしいのだが、何か強烈に惹きつけられる魅力も感じた。
熊送りには熊を狩った時に行う儀式と、飼いならした子熊が大きくなって殺す時に行う儀式があるという。後者は特に残酷さが際立っている。写真を見るとまだ子供の熊も対象になっている。現代なら動物愛護団体の抗議の対象になりそうだが、私達だってまだ子供の生き物を食べ物として取り入れていることはあるし、残酷さには変わりないのだ。むしろ残酷さから目を背けない所に学ぶべき所もあるかもしれないと感じた。
仔グマ飼育型クマ送りはいつから
広く北部ユーラシアから北アメリカに至る北方地域における北方諸族の問では、山猟でクマをしとめた場合にその場で解体し、頭骨をはじめとする骨をその場で天の世界に送り返す儀礼を行っている。これは「オプニレ型」と呼ばれる動物儀礼である。これに対して「オマンテ型」とされる儀礼は「仔グマ飼育型クマ送り」を指し、きわめて特殊なもので厳格な規律の中で行われる最高のスタイルの儀礼とされる。 母グマは冬ごもり中に仔グマを出産する。アイヌの人たちは、春先にその母グマを殺し、山でその送りを行い、仔グマを集落に連れ帰るのである。北海道の場合はその仔グマが二歳になった冬に—樺太(サハリン)の場合は三歳まで育てることがあるというが—、それを殺して送りを行うのである。それが「仔グマ飼育型クマ送り」であり、一般的にいうイオマンテ(イヨマンテ)である。
オホーツク「クマ祀り」の世界 – OKHOTSK
イオマンテの⽅法は、⼭でクマを獲った場合と飼育した場合があります。⼭でクマを送るときは、⽳にこもっている成獣が対象となります。このとき、⼦グマがいる場合があります。その場合、⼦グマを決して殺すことはなく、村(コタン)に連れて帰り、1〜2年もの間、⼤事に飼育します。1〜2年後の2〜3⽉ころに、先に送った親グマが住む神の国(カムイモシリ)へ送るのです。
2021年度札幌⼤学学芸員課程 企画展 『共創 〜カムイとアイヌと動物と〜』 オンライン展覧会 儀礼編① クマ送りの起源 ―オホーツク⽂化の⾻塚よりー
白老周辺では、悪心を起こして人を襲ったのか、自衛上やむを得ず襲ったのか、出来心であったのかを判断し、その度合いによって処置し、音更(おとふけ)のアイヌは、爪や牙が欠けているのはクマが何か悪事を起こした証であり、例えば歯牙の欠けなどの異常が2個あった場合には、このクマは神に対して2度罪科を犯したものと判断したそうです。
獲ったクマの身体についても、徹底的に調べられ、牙や爪が欠けているような異常があれば人を襲った証拠としました。
凶暴なクマの亡骸(なきがら)は野ざらしにされ、埋葬することもなく腐敗するに任せて放置されたり、肉を切り刻んで周囲にぶちまけ、鳥や犬が食べるのに任せたり、皮を裏返しに剥いで葬るなど、どの地域のアイヌにおいても、そこに神を崇めるという姿は見られません。
動物や植物だけでなく、お椀などの道具が壊れたときでさえ簡易な送りをするアイヌにとって、山の最高位の神であるクマの霊を送らないということは、異例中の異例だと言えます。
「キタキツネの霊送り」なんてものもあるんだな。しかも「1986年に道東の美幌峠で行われた」なんて、結構最近じゃないか。オホーツク文化は5〜13世紀にサハリン南部、北海道オホーツク海沿岸、千島列島にかけて展開した⽂化で、ヒグマのイオマンテ(霊送り)もその頃から行われていたらしいが、それを1986年に一時的に復刻させたのか。「当時のアイヌの人達もほとんど知らない幻の祭り」という断り書き付きというのは、イオマンテ自体はだいぶ前に廃れてたのかな。
アイヌの「幻の祭り」チロンヌプカムイ イオマンテ(キタキツネの霊送り)が映画としてよみがえる
1986年に北海道・美幌峠で撮影
シベリアの木製口琴と金属製口琴 北方民族博物館の館内映像(撮影可)
ケット/西シベリア Ket/ Western Siberia 木製口琴 Wooden jew’s harp
サハ/東シベリア Sakha/Eastern Siberia 金属製口琴 Metal jew’s harp
↓訪問時はわからなかったが、2番目の動画の右側にいる男性は口琴奏者スピリドン・シシーゲン(Spiridon Shishigin)さんだとわかった。その世界では有名な人だった。YouTubeにもいくつか動画があり、CDやDVDなども出ているが、ビデオ類は入手困難なものが多い。
参考:Spiridon Shishigin _ ディスコグラフィー _ Discogs
ロシア/サハ共和国 金属製口琴 中国/内モンゴル自治区/ハイラル区 エベンキ 金属製口琴 ロシア/ハバロフスク地方 ナーナイ 金属製口琴
北海道/常呂 サハリンアイヌ 竹製口琴 北海道/網走 北海道アイヌ 竹製口琴
口琴はムックリともいうと後に知った。北方民族博物館の売店でムックリが1000円で売られていたが、その時はムックリが口琴だとわからず、子供用のおもちゃか何かだと思って気になったものの買わなかった。その後、Amazonや楽天などでも口琴が安く売られていると知ったが、せっかくなら北海道の現地で買いたかった。
結局、その後ネットで探してアイヌの竹製のムックリを購入してみたが、音をだすのがなかなか難しい。腕がすごく疲れてくるのだが、力の入れ方のコツとかあるのか?あと口でくわえた時に弁があたってかなり痛い。→狂ったようにブンブン引っ張っていたら一瞬倍音っぽい音が鳴り、音色の変化も付けられたが、再現できる自信はない。
これも独特で面白い。
道の駅 流氷街道網走 オホーツクの観光協会で見かけた小さなニポポに一目惚れして即購入。
6cmのキーホルダーと金具なし人形両方。
6cm 税込561円
キーホルダー 税込671円
9cm 税込781円
12cm 税込1001円
15cm 税込1221円
網走観光協会から買ったものは網走刑務所製作の刻印が入っていて、刑務所作業製品であることの説明書が付いてた。木材は槐(延寿)。ニポポが入った柄の手ぬぐいが気に入ったので書いたかったが、もうこれは在庫切れなのだそうだ。他の色なら在庫があったが、オレンジ色が一番自分好みだったので購入は見送り。
網走刑務所制作なら網走刑務所作業製品展示場に行けばもっとたくさん種類があるんじゃないかと思って後に出かけてみたが、残念ながらニポポやそれに類似する製品は1つもなかった。店員さんに聞いてみたが、ニポポは置いてないので欲しいなら観光協会に聞いてみてと言われた。となると、現時点で網走刑務所製のニポポを最も多く置いてる場所は道の駅 流氷街道網走 オホーツクということになるのかな。残念。ただ網走刑務所正門の展示スペースにはニポポの制作段階の見本品が置いてあった。
網走セントラルホテルの鍵もニポポだった。これも網走刑務所製のようなのだが、あまり見かけない。どこで売ってるのだろう。
道の駅 流氷街道網走 オホーツクであばしり牛乳を飲む。甘さを感じる味ですごく美味しい。飲んだあと、瓶もお土産として持って帰る。
網走郷土博物館に行ったら受付にミニチュアのモヨロ土器があり、これも気に入ったので購入。おそらく手作りだと思うが、大きさも模様もまちまちで、歪なものもあり、そこが味になってて良い。選ぶのが楽しい。館内にかなり個性的なニポポも展示してあった。
網走郷土博物館は建築家田上義也が設計した希少な建造物で、国の登録有形文化財だが、あまり古さを感じさせない外観に改修されている。内部は特徴的な螺旋階段などがあって見ごたえがある。入館料が120円と安いのもありがたい。
網走駅前の街灯もニポポだと聞いてはいたが、目が悪いことに加え、かなり小さいので肉眼では見つけられなかった。次行った時に確認して写真撮ってこよう。ただし網走駅前郵便局と網走大曲郵便局の風景印のニポポはGETできた。良かった。
西三プラザのニポポと海産物北都の看板のニポポ
建て替えが決まっている網走市役所の標語タワーのニポポ。これもいずれ解体されるんだろう。網走市役所の外観は何となく釧路駅に似ている。展望台のような楼閣があるのが気になって市役所職員の人に聞いてみたが、上階には行けないとのことだった。
網走川 大曲橋のニポポ
大曲橋 左の橋は自転車道
網走川 鏡橋のニポポ柵
天都山のニポポ
大広民芸 木彫朔峰の店に寄ってみたが、かなり品薄で目当てにしていた小物類がまったくなく、店主さんは他のお客さんと話し込んでいたこともあり、在庫をお尋ねすることもなく店を出てきた。
その後、大広民芸のパシカっぽいこけしを中古で見つけて購入したが、署名などもなく、これが大広民芸のものなのかどうかは分からない。次回訪問した時に大広民芸の小物を入手できればいいなあ。
参考:大広民芸店(Wayback Machine)
奄美の旅最終日。
行程
おがみ山公園に近い名瀬(なぜ)の久里町(くさとちょう)に泊まり、そこからおがみ山展望台に登ってみる。すべてのコースを踏破はできなかったが、名瀬港を一望できる景色は想像以上に素晴らしく、熱帯特有の公園内の植生も興味津々、大変有意義な小時間を過ごせた。
おがみ山公園には裏口の方から登ってみる。住宅街の中にある古びた半開渠が気になる。
21時までやってるビギナーショップというお店で、雑貨屋さんらしい。気になる。
車両進入禁止の警告があるが、車両と言ってもせいぜい2輪車しか通れなさそうな山道。
登っていくと段々景色が良くなってくる。
中央の巨大な建物は平成元年(1989)築の奄美小学校の校舎。校内放送が響き渡ってくる。
参考:奄美小学校の歴史
投石禁止の看板
展望台に達すると名瀬港側の風景が一気に開ける。古仁屋行きのフェリーに乗ったターミナルも見える。
小島の灯台は名瀬立神灯台。
参考:鹿児島県奄美大島 「名瀬港立神灯台」 – 「九州・沖縄 ぐるっと探訪」
この石垣はサンゴだろうか…?
普通の石垣にも見えるが、妙な網目模様の繊維質があるので…。その上には野生のカランコエ不死鳥が生えていた。
名瀬永田町(ナゼナガタチョウ)側に降りる階段。
昭和天皇の御野立記念碑(昭和2年)
参考:文化財・史跡案内/鹿児島県奄美市
横綱朝汐昇進記念碑
参考:文化財・史跡案内/鹿児島県奄美市
関東地方では見かけないような、巨大なシダやソテツやシュロ系の植物が生えまくっている。こちらもかなりの高木だが、幹の目玉模様が葉が取れて根上がり(?)幹上がり(?)したモンステラの目玉模様っぽく見える。こんな模様がデフォの植物があるのか。望遠レンズが壊れてしまったので蛇の目模様(目玉模様)を拡大できない。
ラピュタに出てくるみたいな巨大な木。ガジュマルか?気根がすごい。御神木と呼ぶに相応しい威厳がある。
豊島榮翁胸像
ツル化したモンステラに寄生された樹木。関東地方などの花屋で売られている観葉植物としてのモンステラは地生状態の鉢植えが多いが、こちらは完全にツル化している。
なんという太い茎…これもう完全にツタだろ…
普通の気根とは違うような細密な根が幹を張っている。これも着生用の根なのか。
写真がわかりづらいが、寄生された木の全容。ここにツタ化したモンステラが寄生している。
名瀬港(名瀬永田町)側にも投石禁止の看板。そんなに石投げるのが好きな人がいるのか。
久里町(くさとちょう)側の登山口には案内板は何も設置されていないが、名瀬永田町(なぜながたちょう)側には立派な案内板が設置されている。
永田川に架かる名瀬永田町(なぜながたちょう)側登山口の橋と門柱。
永田川
永田川に架かる上之岸橋(じょうのきしはし)
欄干が低い昔の橋。
参考:全国Q地図
昭和35年10月2日架替換
施工 竹山建設
竹山建設は今も奄美地方で港湾工事・土木工事・民間建築工事などを請け負っている大規模な総合建設会社のようだ。
風景印を集めに永田橋郵便局に向かう。
途中の大島高等学校前バス停。
大和村直行バスのバス停でもある。
時刻表
永田橋郵便局
小洒落た洋風レストランにも見える建物で、左上の電線が遠目に筆記体の店のロゴに見えてしまった。
ポスト型はがきを買って風景印を押してもらう。
諸屯郵便局でもらった「郵便局を5か所巡って局名スタンプを集めよう」の用紙にも局名印を押してもらう。こういうのって鉄道の途中下車印を押してもらうのにも似た感覚があるな。
参考:【スタンプラリー】奄美群島63局の風景印を集めよう♪|日刊しーま 奄美群島のディープでゆるい情報まとめ
参考:シマ旅で奄美再発見 20コロナ禍の夏を行く① – 奄美新聞
参考:風景印、取り扱い開始 奄美の63郵便局 伝統芸能、風景描く|南海日日新聞
奄美地方にはすべての郵便局に風景印があるらしく(簡易郵便局は不明)、諸屯郵便局でプリントアウトしてもらったスタンプラリー用紙にも風景印を押してもらう。
窓にばってん印の養生テープで補強してある家が多いのは、やはり台風が強いせいかな。
イノシシ、島ヤギ肉などを取り扱っているミートショップ重田。お腹がすいたので空港に向かうまでに小腹を満たせる物はないかと思ったが、メンチカツ類はないと言われてしまった。そういう軽い揚げ物類はないようだった。本格的な肉は美味しそう。
しまバス永田橋バス停は上下線ともミートショップの目前にある。
時刻表
元治青果店
今はどこの店頭にもタンカンが所狭しと並んでいるが、ここもタンカンだらけ。寄りたかったが時間がなかった。古びた店構えだが、ピーチの特集にも載っている。
参考:こだわりの奄美品質。名瀬の見逃せない名店巡り! — PEACH LIVE
24時間無休の奄美コインランドリー。
しまバス本社前バス停
ここからしまバスに乗って屋入銅山跡に向かう。
赤木名外金子久行き
しまバス本社前9:45発 乗車
屋入ひさ倉前10:11発 下車
運賃700円
しまバス、土地勘のないよそ者には時刻表が難しすぎる。
とてもレトロなトラの絵が描いてある降車ボタン。これは良いボタン。イラスト入りのバスの降車ボタン、↓こちらのページに乗っていない所を見ると、わりと珍しいのかな。…と思ったが、和歌山バスでも同じものが使われているらしい。
参考:BUS STOP No.17 懐かしくなるバスの降車ボタンの数々|公益社団法人日本バス協会
参考:和歌山バスの降車ボタンがSNSで話題に キャラクター名は「くボお」? – 和歌山経済新聞
押した時にうっすら浮かび上がる赤いランプもイイ。
屋入ひさ倉前バス停(奄美空港方面行き)で下車。対向車線側には屋根付きの待合室もあるが、空港方面行きにはない。のどかなバス停だが、交通量が多く、飛ばす車も多いので、バス停前はあまりのどかな雰囲気に浸れない。バス停前には「けいはん ひさ倉」という料理店1軒しかないが、ここは奄美大島の郷土料理店のようで、観光バスの団体客が多数訪れていた。
「わきゃシマの宝 屋入集落」の立派な案内板がある。
これから向かう屋入(やにゅう)銅山跡も掲載されている。案内板が設置されているということは、場所がわからなくて戸惑うということはなさそうか。
龍然町の中でも、屋入のサギジャほど今昔の感にたえない場所はないという人もいます。サギジャの奥のカジヤヤシキの裏手にある地面が青みかかっているところは、草木もまばらで山上の砂浜のようになっています。その一角には、3アール程の広さの空き地があって、中心部に銅を溶かした炉の跡があります。この地点から更に小道を奥へ行くと鉱山の坑道の入り口が残っています。
ソテツの無人販売所があった。すべて1鉢500円。
ヤフオクでも少数ながら販売されている。
屋入(やにゅう)銅山跡に向かう途中にあった廃施設。窓など見るとそんなに古い施設にも思えないのだが、すっかり樹木に飲み込まれているのは生育スピードが異様に早いせいか。
加計呂麻島同様、サクラは散りかけている。
屋八公民館。裏には気象庁津波地震早期検知観測局がある。
目前の龍郷湾(たつごうわん)は波がほとんどない穏やかな浅瀬でとても美しい。
銅山跡への道標も設置されている。ここを右に曲がる。
銅山案内とともに「さぎじゃ」という道標もあり、何のことかと思ったら、「さぎじゃ」というお茶処の案内であった。が、本来の「サギジャ」の言葉の意味がわからない。お茶処の「さぎじゃ」の方は訪問時に営業している様子はなかった。閉業してしまったのか、期間限定営業なのか。
営業している様子のないさぎじゃの方から定期的にカタンという音が聞こえてくるので鹿威しでもあるのかと思って覗いてみたら、誰もいない静かな庭園で竹筒が水をためてコーンと音を鳴り響かせていた。巨大な熱帯樹木と和風様式の折衷庭園で、摩訶不思議で面白い味わいがあった。
人間の背丈より高いシダ植物が生えている。
さぎじゃを抜けて屋入(やにゅう)銅山跡の方に向かうとまもなく平地が出てきて古びた風呂桶などが出てくる。
木橋をわたった左側に銅山跡はあるのだが、私は気づかずにそのまま山側に突き進んでしまった。
まだ若そうなひょろ細い木にパパイヤらしき実がなっていた。
とある木の幹に直径10cm位ありそうな空洞がいくつもボコボコとあいていたんだが、これはキツツキの巣穴だろうか?しかし「キツツキ 穴」と検索したらキツツキが木の幹に無数のドングリを埋め込む画像(閲覧注意)が出てきて、鳥肌が立った。これは気持ち悪い…。
人間の背丈より高い巨大なシダ植物が生えている。
ゼンマイの部分など人間の手の拳大ほどもあり、恐竜時代にタイムスリップしたようだ。どうやらヒカゲヘゴらしく、食べることもできるようだ。
大型の常緑木生シダで、日本では最大のシダ植物である。鹿児島県の奄美大島や沖縄県の沖縄本島から八重山諸島にかけての森林部でよく見られる。
ヒカゲヘゴ – Wikipedia
暫く山道の方を突き進んでいたが、人の踏み跡も定かでなく藪が生い茂る山林を普通の服装で歩むのも困難と判断して戻ってきたが、銅山らしき片鱗はないかと探しながら戻ってくるくるうちに、木橋から程遠くない山壁にひょっこり穴があいているのを見つけた。穴が真っ暗になる時間帯で気づかなかった。
左手にきれいに成形された2つの抗口が見える。中は静かで水の滴る音だけが響いている。
配管もそのまま残っている。
よく見ると足元に「3 銅鉱山」の案内板もあった。
屋入ひさ倉前バス停までピストンで戻ってくる。
途中、屋八公民館裏にある気象庁津波地震早期検知観測局に立ち寄ってみる。
再びソテツ無人販売所に戻ってきた。よく見たらちゃんとレジ袋も用意してあった。けいはん ひさ倉に来た団体観光客が興味を持って見ていた。
屋入ひさ倉前バス停(奄美空港方面行き)から再びしまバスに乗って奄美空港に向かう。
赤木名外金行き
屋入ひさ倉前バス停 11:41
発奄美空港 12:01発
運賃570円
バスは7分ほど遅れて到着した。路線バスにしては珍しく(?)「遅くなってすみませ~ん」と謝る運転手さんだった。
整理券 37番
このバスの降車ボタンはトラではなかった。でも好きなタイプ。
バスから見た送信所側無線塔。本当はここにも立ち寄りたかった。
奄美空港で下車。このバスは赤木名外金行きだからここが終点ではない。よそ者だと「奄美空港行き」以外のバスに乗っては行けない気がしてしまうから、難しい。
飛行機の荷物の重さ対策のため、途中で買ったタンカンを空港で消費する。タンカン美味いよな~。いよかんの味に似てる気がするが、いよかんより小ぶりか?荷物制限がなければ持って帰りたかった。
奄美空港の総合案内所に置いてある記念スタンプを風景印押印済みのポスト型はがき計5枚(名瀬郵便局、諸鈍郵便局、押角郵便局、古仁屋郵便局、永田橋郵便局)にも押す。慌ててうまく押せなかった…もっと気を落ち着かせて押すべきだった。はみ出てしまった。
保安検査所を通過後の奄美空港の売店にも園芸コーナーがある。「田中一村が愛した蘇鉄」とあるが、ソテツに見えないものもある。
参考:奄美大島|孤高の天才日本画家、田中一村が愛した南海の絶景と太古の森を歩く – YAMAP MAGAZINE
売店の書籍コーナーで気になった本いくつか。もう少し、郷土資料寄りの本が見たかった。
飛行機は通路側の席だったので機内モードに設定済みのiPhoneGPSをまったく受信できず、ずっと九州上空にいるつもりでいたが、いつの間にか関東上空まで移動していて「着陸体制に入ります」との案内放送がかかってびっくりした。Peachの場合、成田空港から奄美空港に向かう時の飛行時間は3時間と設定されているが、奄美空港から成田空港に向かう時は2時間と設定されている。偏西風の影響らしいが、夏と冬でもこうした違いはあるらしい。
参考:偏西風と飛行機 夏と冬 ダイヤなぜ違う?:東京新聞 TOKYO Web
参考:飛行機で北から南へ行くよりも南から北へ行くほうが近いのはなぜですか?… – Yahoo!知恵袋
京成電鉄
成田空港駅スカイライナーの広告
京成八幡駅で乗り換え
きっぷに無効印を押してもらう。
京成八幡駅で専用の駅巡りスタンプ帳に駅スタンプ押印。
渋谷の東急本店と立川高島屋と帯広の藤丸百貨店が本日をもって営業終了した。藤丸は創業以来122年の歴史があり、道内最後の百貨店でもあり、閉業の風景がライブ配信されていた。自分にとってはダイエーのようなスーパーマーケットほど馴染みのある店ではないが、当たり前のようにそこにあった風景が消え去っていくのは寂しい。ライブ配信を見ていたらダイエーの閉店セールなどを思い出してじんわりきてしまった。
近年だと、立川高島屋は昨年8月7日スマホを修理しに立川へ行った時、渋谷の東急本店はアップリンク渋谷へ「3月のライオン」を見に行った時とBunkamura ル・シネマへ映画「カブールのツバメ」を見に行った時、藤丸百貨店は昨年1月31日帯広郵便局に行った時に立ち寄った(帯広郵便局は局員がコロナ感染して閉鎖していた)。Bunkamuraと東急本店は一応違うが。立川の高島屋は平成6年築なのでそこまで古くないが、古びて見える屋号銘板が良かった。
立川 高島屋
渋谷Bunkamura
【惜しむ声】渋谷の東急本店と立川高島屋、31日で営業終了https://t.co/9isuS3SdaG
東急百貨店によると、本店は解体され、跡地には地上36階地下4階建ての複合ビルが予定されている。立川高島屋ショッピングセンターは31日、売り場の約3分の1を占める百貨店区画の営業を終える。 pic.twitter.com/yqT67ga51s
— ライブドアニュース (@livedoornews) January 30, 2023
↓高島屋はないが、一連の記事が面白い。
1年ぶりにのぼりべつクマ牧場に再訪。昨年1年有効の会員カードを作ったので、今回は1000円で入場。
階段の登り口にある廃店舗の看板。コロボックルっぽい味がある…
そういえば、最近「アイヌ」という言葉はよく使われるけど「コロボックル」という言葉はとんと聞かなくなったな。なぜだろう。
こちらは昭和43年5月に建設されて廃止された観光リフト。本来は現在のロープウェイ乗り場まで行けるケーブルだった。でも短すぎるので縮尺の小さい地図には載っていない(参照:今昔マップ室蘭1986-1987)。
こちらは現在の登別温泉ロープウェイ山麓駅
登別温泉ロープウェイ山麓駅で記念スタンプを2個押印
登別温泉ロープウェイ名物「鮭とば号」
のぼりべつクマ牧場のヒグマ達にあげるおやつの鮭とばを冷たい風雨に晒して作っている。
この藁葺小屋のようなゴンドラは春から秋にかけて運行している「カントチセ号」。アイヌの伝統的な家屋である「チセ」をイメージしたゴンドラで、2020年7月18日より運行スタート。昨年来た時はこのカントチセ号の中にも鮭とばが吊るされていたが、今回はクマのヌイグルミが置かれているだけだった。
延々と見入ってしまう。
一廻りするのにおよそ20分ほどかかる。
山麓駅ののりば付近にいると下りと上りの往復分を見ることができる。
10分ほどたつと今度は実際に鮭とばを吊るしたゴンドラ「鮭とば1号」がやってくる。「カントチセ号」と「鮭とば1号」が10分ごとに交互にやってくる計算。やっぱり実際に鮭とばを吊るしているのはいい。見入ってしまう。
のぼりべつクマ牧場の冬(10月21日~4月20日)の営業時間は9:30~16:30で、最終入場は15:50だが、山麓駅付近で1時間ほど鮭とば号などを眺めていたりしたら肝心のクマ牧場をゆっくり見学する時間がなくなってしまった。考えてみたら山麓駅での見学は別にロープウェイの利用客でなくてもできるのだから、もっとクマ牧場の見学に時間かければ良かったな…
前回来た時も鮭とば号のすぐ前に乗ったが、今回もできるだけ鮭とば号の近くで乗りたかったので、10分ほど時間調整して鮭とば号が来るのを待つ。他にお客さんがいないので好きな時に乗れる。係員の人に鮭とば号のすぐ後ろに乗りたいと言ったら「先に乗った方が降りた時にゆっくり見れる」とアドバイスを頂いたのでその通りにしたら降車時に入場してくる鮭とば号をじっくり見れて良かった!
前回来たのは2022年1月29日だが、その時より雪が少なく、鮭とばの鮭はまるまる肥えていて、鮭とば号も新調されたような感じになっていた。
右の鉄塔は廃止された古い索道
鉄骨感が良い味わいしてる
しかしここで元々調子の悪かったカメラが壊れてしまった
何とかiPhoneで撮影する
すっかり夕陽になってしまった
上からやってきたカントチセ号とすれ違う~
カントチセ号と鮭とば1号がすれ違う瞬間を撮影できた~
ロープウェイ山頂駅の降車場で降りる
後ろから迫ってくる鮭とば号をゆっくり観察する
まるまる肥えた鮭とばが目の前を過ぎ去ってく~
ぐるっと回って行ってしまった…
季節に応じてハロウィン号なども運行しているようだ
ロープウェイの仕様
登別温泉ゴンドラリフト
線路斜こう長 1260.75m
最大高低差 294.97m
運転速度 毎秒5.0m
原動機 300kW
往者定員 6人
毎時輸送量 1800人
竣工 平成2年4月
事業者 登別温泉ケーブル株式会社
設計・施工 日本ケーブル株式会社
北海道の他のロープウェイ
行きたい…
登別温泉ロープウェイ山頂駅
山頂の気温は-2℃。あまり寒くない。
山頂駅目前のヒグマ博物館
残り時間20分程度しかなく、あわてて前回見きれなかったアイヌ生活資料館などを回ろうとしたが、前回より規模縮小していて見学できる場所が少なくなっていた。
ヒグマ博物館で記念スタンプ1個押印
ヒグマ博物館
展示物を多少リニューアルしているようにも見えたが、今回は時間がなくてまったく見学できなかった
ヒグマ博物館の展望台から見えるまあるいクッタラ湖(倶多楽湖)
「ヒトのオリ」のエリアにいるオスのヒグマ2頭が絡んでいた。ケンカでもするのか?と見ていたが、何事もなく絡むのをやめた。遊んでいたのか?しかしこんな雪のちらつく中でもヒグマ達は何事もなく活動している。この調子では、野生のヒグマも「冬季だから」といってあまり安心できないのでないか?と思ってしまった。もっともヒグマは他の動物と違い、冬眠しても眠りが浅く、すぐ目覚めてしまうようなので、冬季でも油断は禁物だ。
参考:冬眠しないヒグマを警戒 北海道東部の冬の工事現場から – NHK北海道 2022年2月10日
せっかくおやつをもらったが、閉園15分ほど前にはもうヒトのオリの中には入れなくなっていた。上から眺めることはできるので、上からおやつを投げ入れた。他のオスヒグマ達は遠慮しているのか寄って来ず、1頭のヒグマにしかあげられなかった。結構うまくキャッチして食べてくれたが、カラスにもおやつを持っていかれてしまった。
おやつをあげたオスヒグマの顔、雪の反射効果でiPhoneの望遠レンズでも意外とよく撮れた。
ロープウェイの終便が16:25。ギリギリに駆け込む。帰りのロープウェイまわりの風景はすっかり薄暗くなっていた。
二俣尾の多摩書房が閉業していた。11月に閉業したようだ。ショックすぎる…。言葉が出てこない…
〒198-0171 東京都青梅市二俣尾4丁目1098
近くの火の見櫓
青梅市消防団 第5分団 第1部
その後、八王子の佐藤書房に立ち寄り、古本3冊購入。21時まで営業だと思っていたが、20時までだったようだ。Twitterの店舗紹介には営業時間11時~21時と書いてあるが、Googleには11時~20時と書いてあるので、時間短縮したようだ。佐藤書房の紙袋に描いてあった猫が可愛らしい。
東京人の同潤会アパート特集。2000年9月号。500円。私は原宿にあった同潤会アパートを知っているのよな…まだ解体前だった。写真を撮って於けば良かった。
先日、苫小牧あたりを散策して、いろいろ調べてたら八王子千人同心と勇払原野が関連あることを知り、以外に思ったが、その矢先に佐藤書房で「蝦夷地ゆうふつ原野」という本を見つけ、あまりにもよくできた偶然のように感じて購入。でも1000円という価格は相場より安いようだ。良かった。
1975年の山と高原地図 奥多摩
うちにあった気もするが、110円ならもう1つあっても良いだろうと思い購入。ただ1/50000は縮尺が小さすぎるな。
WordPressのiOSアプリがあまりに使いづらいので、暫定的に他社のブログサービスを試している。PCで投稿する際はWordPressの方が圧倒的に便利で応用効くが、スマホアプリだと自分の場合は他社ブログサービスのアプリを利用した方がマシな面がある。現状はlivedoor Blogで落ち着きそうだ。
WordPressのモバイル版が使いづら過ぎて、使いづら過ぎて…
PC版は高機能で良いけどモバイル版はTwitterにも遥かに劣る使い勝手の悪さ
気軽に投稿もできない
長節湖の遊歩道
「遊歩道」なんて口ばかり
地形図にはまだ道の記載が残っているが
入口がロープで閉鎖されてる時点で察したけど
遊歩道はもう朽ちて道筋を探すのが困難な所もある
湿地帯は凍っていたおかげで何とか行けたけど、秋ならズボッと足がはまったはず…
道筋に石碑や石仏が点在しているが、これも朽ちていくばかりか…
冬とはいえ比較的気温も高めで(6〜7度くらい)ヒグマが出てこないかという恐怖感もあったので途中で戻ってきた
荒天でまた陰鬱な雰囲気だし
これから更に風速13mほどの暴風雨になる予報が出ていたので
こちらは海沿い
予想通り潮が高くてたどりつけず
風速10m以上の暴風雨になる予報が出ていたが、この時点でかなり風が強く、上から小石が大量に降ってきて顔に当たって痛いし落石の危険性も感じ途中で引きかえした
しかし凄い地層だ
歪曲している
太平洋フェリーきたかみで仙台港から苫小牧にアクセスした。苫小牧西港の工業地帯の風景は何度見ても見入ってしまうが、昼に着港なのでフェリーの係留作業の様子もよく見れてとても面白かった。
苫小牧西港フェリーターミナル 太平洋フェリーきたかみの係留作業。面白くて、下船ギリギリまでデッキで見入ってしまう。気温もまだそこまで低くなかったので助かった。
苫小牧西港フェリーターミナルで路線バスの発車時刻までいろいろ見ていると、太平洋フェリーの船員の女性が「キツネがいる」と教えてくれた。急いで見に行ったが既にカラスしかいなかった。お姉さんは「カラスに攻撃されて逃げたかも」と教えてくれた。
苫小牧西港フェリーターミナルバス停から路線バスに乗り、駅通十字街バス停で降りる。約10分、250円。もう少し時間が早ければシネマ・トーラスで映画を観たかったのだが、上映時間に間に合わず、あきらめて駅通十字街から銭湯松の湯まで、錦町、大町、本町あたりの歓楽街を観て歩くことにした。
この辺は明治、大正時代以降に、王子製紙工場の社宅建設にあわせて整備された市街地で、特に錦町、大町あたりは昭和後期に発展している。
明治、大正時代には幸町、浜町のニヶ所に分かれて遊郭地が存在していたが、幸町の方は大正10年の大火で焼失している。
苫小牧の遊郭の歴史については、「苫小牧市史 下巻」が詳しい。遊郭の建物が王子製紙工場の社宅になったりと、二人三脚の歴史を刻んできたようだ。戦後、それらの遊郭が形を変え、錦町、大町にある新一條通り(親不孝通り)の歓楽街に進出したため、そのあたりはどことなく赤線跡のような雰囲気もあるが、古い建物は大分解体され、最盛期の面影を偲ぶのは難しくなってきている。しかしそれらの建物の合間から今もモクモクと煙を上げる王子製紙工場の大煙突を眺めるのはとても感慨深い。
苫小牧市史 資料編 第2巻 1977年3月 苫小牧市編 国立国会図書館デジタルコレクション(個人送信サービスで閲覧可能)
P.27 苫小牧5万分の1図(明治29年)[北海道立図書館蔵]
P.29 苫小牧5万分の1図(大正8年・昭和19年修正)[堀江俊夫蔵]
P.30 苫小牧町管内畧圖(明治45年・苫小牧村)[堀江俊夫蔵]
P.31 苫小牧町管内畧圖(昭和7年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵] /膽振支廳管内圖抄(昭和11年・膽振支庁)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.32 苫小牧町管内圖(昭和15年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵]
P.33 苫小牧町字名改称圖(昭和18年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵]
P.34 苫小牧要図(昭和44年・苫小牧市)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.35 苫小牧村畧圖(明治40年・勇払郡名村市街地略圖)[厚眞町真正寺蔵]
P.36 苫小牧市街地電線路圖(明治44年・王子製紙)[堀江俊夫蔵]
P.37 苫小牧市街圖(昭和16年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵]
P.38 苫小牧町町名地番改称圖(昭和18年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵]
P.39 苫小牧市市街図補足(昭和29年~33年・苫小牧市)[堀江俊夫蔵]
P.40 苫小牧市市街圖(昭和31年・苫小牧市)[堀江俊夫蔵]
P.41 苫小牧市市街図(昭和40年・富士波出版)[堀江俊夫蔵]
P.42 苫小牧新町名全図(昭和49年・ハギ健康堂)[堀江俊夫蔵]
P.46 道内における王子製紙経営鉄道配置図[王子製紙社史第4巻]
P.47 苫小牧管内道路網圖(大正15年・苫小牧町)[堀江俊夫蔵]
P.86 渋川又平作成の明治末期より大正にかけての苫小牧市概略図[市立苫小牧図書館蔵]
P.87 苫小牧大火概況図(昭和52年・田中平美作成)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.89 苫小牧案内(昭和12年・苫小牧商工会)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.121 苫小牧市々街案内図 昭和31年12月1日現在 北海道交通社出版局
P.125 苫小牧町案内圖 昭和9年3月現在 苫小牧商工會
堀江俊夫さん所蔵の地図が多いが、「苫小牧地方鉄道史」の著者の堀江俊夫さんか…
苫小牧市史 下巻 1976年 苫小牧市 国立国会図書館デジタルコレクション(個人送信サービスで閲覧可能)
P.2 苫小牧案内(昭和12年・苫小牧商工会)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.25 明治35年ごろの苫小牧の商店街
P.33 大正10年大火時の苫小牧中心部概要図
P.62 錦町商店街(昭和29年)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.66 飲食店が建ち並ぶ親不孝通り(昭和50年)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.69 一条銀座商店街(昭和51年)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.74 明治末期の商店街/大正時代の商店街/昭和前期の商店街/昭和後期の商店街
P.75 現在の主要商店街
P.90 新設になった苫小牧市公設地方卸売市場(昭和50年)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.96 一条銀座商店街(昭和46年・昭和51年)[苫小牧市史編さん室蔵]
P.97-108 第三節 遊郭の変遷 戦前の遊郭/戦後の遊郭
樽前山 : 甦える火の山-その自然と人間の記録 竹馬敏広 著 苫小牧郷土文化研究会 1979.8 国立国会図書館デジタルコレクション(個人送信サービスで閲覧可能)
P.36 王子製紙苫小牧工場と樽前山
目でみる苫小牧の百年 : 苫小牧市開基百年記念 苫小牧市市史編さん室 苫小牧市 1973 国立国会図書館デジタルコレクション(個人送信サービスで閲覧可能)
P.37 娯楽・遊興
P.105 一条商店街の形成の契機になった鶴丸デパート(昭和31年)
P.65 舗装前の錦町一条通り(昭和30年)
王子製紙㈱ 苫小牧工場社宅街について 日本建築学会計画系論文集 第619号 165-172 2007年9月
錦町出雲神社は新一條通り(親不孝通り)にある神社で、明治45年に建てられた。竣工当時は鬱蒼とした樹林の中にあり、沼もあったらしい。かつてもっと広かった境内はいずも公園の敷地となり、公衆トイレも設置されている。逆に神社のほうがおまけのような雰囲気に見えてしまう小ぶりさだが、味わいはある。山口時計店は社務所の名残りらしい。地元のお婆ちゃんが参拝していた。
苫小牧の錦町・大町・本町あたりの商店街&歓楽街。新一條通り(親不孝通り)/一条通り(大町銀座ストリート)/二条通り/三条通り。
王子製紙工場・南門と、その近くにある映画館シネマ・トーラス&ボーリング場の中央ボウル。大正時代、このあたりには苫小牧尋常高等小学校があったようだ。
浜町にある銭湯・松の湯で入浴する。先代から80年位やっている銭湯らしい。苫小牧町案内圖(昭和9年3月現在)[苫小牧商工會]を見ると「松の湯」の名が確認できる。2022年は昭和97年なので確かに80年以上の歴史だ…苫小牧市史 下巻には以下のような記述もある。
風呂屋では明治39年まで倉嶋の経営する「松の湯」一軒であったが、王子製紙の工場建設が進展するにしたがい増えはじめ、同43年には5軒、昭和に入ると10軒を超えるようになった。
「松の湯」は苫小牧の銭湯の元祖のようだ。
松の湯(まつのゆ) 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合
〒053-0014 苫小牧市浜町2丁目6-12
TEL 0144-72-4417
営業時間 14:00〜21:00
定休日 毎週月曜、第1・第3火曜
16時頃に入店、まだそれほど客はいないだろうと考えていたら地元のお年寄りで大混雑していた。こんなに活気ある銭湯は久々だ。ちょっと嬉しくなってしまった。昔ながらの番台式の銭湯で、脱衣所も浴室も人がいっぱい。女将さんがとても親切で愛想の良い人で、甲斐甲斐しく常連さんの面倒を見ながらこちらにも色々と案内してくれた。カランのお湯が熱いので自分で水と混ぜて温度調節するようにとアドバイスされたが、シャワーのお湯は冷たさを感じないぬる湯だったので、そのまま髪などを洗った。浴槽はジェットマッサージ風呂と普通の風呂。湯船の湯温は熱め。ぬる湯が好きなお客さんは水を入れて温度調節していたが、熱湯が好きな自分は歩き回って冷えた体を一気に温められて生き返った心地になった。お風呂から上がって着替えていると女将さんが冷たい水をコップに注いでくれた。熱い湯船にじっくり浸った後に飲む冷水はとても美味しい。いつまでもこんな活気ある銭湯でいてほしいと思った。
薄暗くなった街道を、苫小牧駅まで徒歩で移動する。王子製紙工場の煙突は暗くなっても煙を吐き続けていた。王子製紙工場の社宅も煙突と共に夕陽に照らされていた。錦町の駐車場に、ぽつんと山下清(裸の大将)の看板が掲げてあった。不思議に思って写真を撮ったが、こんなエピソードがあるらしい。
登別軟石馬車鐵道
開業 1909年頃?(明治42年)
廃止時期 不明
登別温泉馬車鐵道(登別温泉軌道)
開業 1915年(大正4年)12月1日
廃止(昭和8年) 1933年10月15日
参考
市史ふるさと登別 下巻 登別市史編さん委員会 編 登別市 1985年出版 – 国立国会図書館デジタルコレクション(個人送信サービスで閲覧可能)
P.240 2 中登別・登別地区/928
P.188 8 登別軟石(溶結凝灰岩)/824
登別温泉軌道 – Wikipedia
登別市史編さんだより 第14号(令和2年3月1日) 登別温泉軌道(登別駅前~登別温泉駅)
登別市登別軟石専用線 きのこ屋のHP
北海道の軟石文化をご紹介します。 – 札幌軟石情報発信サイト
北海道 古き5万分の1地形図 失われた鉄路
カモイワッカ 登別市教育委員会
2022年9月末をもって発売終了したJR東日本の回数券を使って奥多摩に行ってきた。
立川駅08:09発のホリデー快速おくたま3号(奥多摩行)に乗ったが、土日の午前中の青梅線はめちゃくちゃ混むのな。立客多数で当然のように座れなかった。御岳駅で大量に降りたが、終点奥多摩駅まで行く客もかなり多い。奥多摩駅の改札口に駅員が二人以上待機してるの自分は初めて見た。
奥多摩駅で使用済み印を押してもらった。押してもらうのは初めてだ。
参考 :普通回数乗車券の発売終了について JR東日本
日原鍾乳洞方面に行こうと思っていたが、東日原行きのバスも大混雑。次のバスは2時間後だが、この日はさしたる予定も立てておらず、景色も見れず混んだバスに乗り込むのも嫌だなあと思って予定していた9:40発のバスは見送った。外国人観光客の姿も結構見かけた。奥多摩駅前の観光案内所に立ち入る利用客も多く、駅前には飲食物の移動販売車も来ていた。
次のバスの時間まで2時間あるので、ブラブラと駅周辺を散歩したり、奥多摩観光案内所でスタンプ押したり。ネットでプリントアウト(割引券印刷用ページ/PDF)もできるが、奥多摩観光案内所に立ち寄ると日原鍾乳洞の100円引き割引券をくれる。
学校道踏切を渡る。梅線36K 848M 巾員3.7M
山の上のほうが少し紅葉してきてるが、派手な紅葉ではない。標高200mの高尾付近の紅葉はいつも12月頃だから、そんなものかな。
時間があるので、奥多摩工業の方に行ってみた。
「除ヶ澤治山工事のお知らせ」なるものが掲示してあった。
除ヶ沢(よげさわ)とは奥多摩工業曳鉄線のトロッコ橋がある付近の沢のこと。
時々沢登りする人もいるようだ。
奥多摩工業の工場は稼働していたが、トロッコは動いていなかった。土曜日だからな…
戻ってきて奥多摩ビジターセンターに寄ってみた。入ったのは初めてだ。結構立ち寄る観光客も多い。記念スタンプ類はなかった。
奥多摩ビジターセンターの向かいにあるサイクリングツアー&レンタル トレックリングという店、今まであまり気に留めてなかったが、レンタサイクルも扱ってるらしい。今度利用してみようかなと思ったが、一番安いコースでクロス、MTB(ブリヂストン)平日2500円、9:00 – 17:00(貸出し受付は15:00まで)。ママチャリ感覚では使えないようだ。
駅前の一松肉店で初めて買い物してみた。
お弁当類は予約が必要なのでいつも購入できなかったが、この日はメンチカツ類を扱っていたので。
メンチカツ2個、カレーパン1個、計500円。
メンチカツ、めちゃくちゃ美味い。また食べたい。
その場で買えるお弁当があればいいのになあ…
奥多摩駅前の土産店「みすず 堂」の店構えが何やら寂しげな感じになったので日除け幌テントの色でも変わったかと後で以前の写真を確認してみたら「手づくり おみやげ みすず堂 0428-83-2015」の看板が撤去されていた。手書きテイストのある看板が良い味を出していたので、ちょっと寂しい。奥多摩駅前にはコンビニがないので(ちょっと離れた所にタイムズマートというコンビニがあるが)、昼食用としてランチパックとオレンジジュースを購入。おにぎりも扱っている店だが、この日は切れていた。
西東京バスサービスステーション(氷川サービスステーション)でなにか食べて行きたかったが、開店が12時…11時半発のバスは逃せないので、諦めることに。羊羹も買いたかったが、荷物になるのでこの日は諦めた。
西東京バス 11:30発
東日原行きのバス車内は混んでいて、発車間際に乗り込んだせいもあるが、座れなかった。景色が見れれば良いかと思ったが、立ち客が多いのであまり悠長に眺めることもできず。土日の奥多摩はあまり良くないな…
バス車内では皆それなりにおしゃべりしていたが、そこまでうるさい話し声でもなかったのに、バス乗務員から「おしゃべりしないで」と注意されていた。コロナ感染症対策のためなのか、それ以外の理由なのかわからないが、大声のおしゃべりでもなかったから驚いた。乗務員が叱った理由が気になる。
終点の東日原バス停で下車。奥多摩駅から運賃480円。観光客がどやどやと降り、目的に散らばっていく。
バス停に貼ってある日原鍾乳洞のポスターは色褪せている。
稲村岩尾根は登山道崩壊のため通行禁止となっている。
日原鍾乳洞へは東日原バス停から徒歩約25分
東日原バス停眼下のくねくね歩道
日原簡易郵便局
土曜日なので風景印あるかどうか訊けず。
東日原バス停付近の岡部酒店 芳城屋 ほうじょうや
青梅警察署 日原駐在所
岩松尾根バス停から登竜橋(一原バス停付近)まで、路線バスはずっと氷川鉱山下のトンネル内を走行するので、周りの景色などはわからないのだが、静和旅館付近からそのあたりの岩場が見える。迫力ある。
道馬場の狭い日原街道を日原鍾乳洞方面に進んで進んでいく。道の両側に古い消防施設や商店、民家などが立ち並ぶ。
道路の下は傾斜なので、民家は這いつくばるようにして建っている
静和旅館
営業してるのかな。気になる風情…
静和旅館付近の民家。恐らく廃屋。いい味出してる…
奥多摩工業アパート
従業員向けのアパートだったようだ
波型の屋根が可愛らしいので日原小学校の体育館か何かかと思ったが、これも奥多摩工業関連施設のようだ
ブルータル建築のように見える煙突も気になる
床も天井も剥がれ、相当に老朽化している。
タコ足の鉱山関連設備?
丹生神社付近の慰霊碑
旧日本陸軍兵の名が刻まれている
詳細不明だが土台に「慰霊碑建設寄附者芳名」と書かれているから戦後に関係者有志が建立したもののよう
丹生神社
日原小学校跡
1994年3月に閉校した木造校舎の小学校。きちんと石碑も建てられているが、近くにブルーシートがかけられ、わりと無造作な感じになっている。
日原診療所
現在も診療しているようだ
診てもらいたい気もするが、地元の人間じゃないとダメだろうか
天目山・酉谷山 登山口 道標
日原街道の方に戻ってきた
途中で見た静和旅館、こちらの建物を見ると営業していそうにも見える
日原街道に戻る
電信柱が天目山・酉谷山 登山口方面への道標になっている
日原街道
萬寿水
日原食糧販売所
日原食糧販売所付近の民家・土蔵
中日原バス停
手書きと思われる停留所名がいい
日が暮れゆく日原街道
先程見た奥多摩工業アパート
日原川を挟んだ対岸の山の斜面が土砂崩れを起こしている。現場にいたらかなり怖そうな…
稲村岩を経て鷹ノ巣山方面登山口
「登山道崩落のため通行止め」と書いてあるが、こちらから下山してきた登山者がいた
日原街道
鍾乳洞バス停および小川谷橋付近
昔はこの辺に見晴亭と西東京バス案内所もあったようだ
日原川の小川谷橋分岐付近にある、釣堀施設か浄水施設か不明
林道日原線と日原街道の分岐にある秩父多摩国立公園日原地区案内図
みすず堂でパンとジュースを買ったものの昼食は食べてないので日原鍾乳洞売店でラーメンを食べる。650円。
15時閉店で鍾乳洞も16時半には受付終了するとのことで、既に15:11を回っていたので悠長に食べる暇がなかった。
ラーメンは昔懐かしのあっさりしょうゆ味。お茶も自由に飲めるので落ち着ける。
日原地区の名産品などお土産類も売っていた。
一石山神社
よる暇がなかった。
一石山神社の湧水。
柄杓が置いてあったので、帰りにここで水をごくごく飲んで帰ったが、今のところお腹を壊したなどの問題は出ていない。
エキノコックスでも蔓延すればこうした自由もなくなるのか…
日原燕岩洞門
2017年完成と新しい建造物だ。
脇に歩行者用の通路も設置してあって安全に通行できる。
Googleストリートビューで確認してみると、まだ洞門が完成していない2010年の撮影なので随分雰囲気が違う。
日原燕岩洞門を抜けた突き当りにある籠岩の石仏群。奇岩の岩窟の檻に石仏が収められている。
籠岩の奇岩、石灰岩なのかな。風化してあちこちポコポコと奇妙な穴が開き、中で繋がっている。
これも鍾乳洞と同じ現象かもしれない。
籠岩から先、林道小川谷線は通行止めになっている。
戻ってきて日原鍾乳洞を見学する。100円の割引券を使い、大人800円→700円に。
日原鍾乳洞は子供の頃に来たことあるかもしれないが、覚えていない。
入ってみて、規模の大きさに驚いたが、洞窟なので通路自体は狭く、夕方でも観光客が多かったのですれ違いに結構苦労し、のんびりと楽しむことはできなかった。
昼間ならもっと人が多くて大変だったろう。
日原鍾乳洞は絶対的に人が少なそうな時間帯を選んで行ったほうが良い。
あと水が滴っていても安全な運動靴で行ったほうが良い。
鍾乳洞を出たらすっかり真っ暗になっていた。16:51。
東日原バス停発のバスの時間は17:30。
ここから約2kmの道のり、送れないようにしないと。
帰りに一石山神社の湧水を飲んで帰った。
のどが渇いていたのでめちゃくちゃ美味い。
薄暗くなった日原街道を戻って東日原バス停まで無事到着。
すっかり真っ暗になっていたが、乗客がそれなりにいたので意外だった。
貸切状態かと思っていた。奥多摩って人気あるんだな。
17:57、奥多摩駅に到着。まだ一松肉店が開いていた。
しかし数分後に閉まってしまった。18時までの営業のようだ。
メンチカツがあれば買って帰りたかったが、ホットスナックのショーケースにはなかった。
奥多摩発の青梅線が18:14なので、それまで駅周辺をぶらぶらと。
本橋青果店も既に閉まっていた。
2022-10-21 興津小学校バス停~釧路コールマイン~鳥居と祠~興津海岸トーチカ~銭湯・望洋湯~望洋住宅バス停 徒歩
3年前に動いている姿を見かけた釧路コールマインのナローゲージ、気になって来てみたが、うんともすんとも動いてる気配がなかった。最近まったく情報を拾っていないが、廃止されてしまったんだろうか。
斜坑稼働しているところをきちんと見たかった
敷地内のそこら辺に貨車が放置してあるのは以前と同じなのだが…
〒085-0811 北海道釧路市興津3丁目7-29
奇岩をくり抜いたトーチカ(コンクリート掩体)
2022年10月21日 時間帯 13:52~14:43
前回来たのが2022年2月1日、その時もほぼ同じような時間帯だったが、その時は潮位がもっと高く、西日も強くてほとんど見えなかった。気象条件に結構左右される。
前回よりマシだったが、この日もトーチカ間近まで迫る波があり、近くまで行けなかった
訪問した時間帯は13:52~14:43。
満潮に近い時間帯だったようだ。
この日の釧路の潮位
2022/10/21
満潮 時刻13:38 潮位119
干潮 時刻06:12 潮位43
干潮 時刻19:37 潮位82
参考:気象庁 _ 潮汐・海面水位のデータ 潮位表 釧路(KUSHIRO)
ちなみに2月1日14:35~14:52頃に訪れた時の潮位(新月だった)
2022/02/01(火) 朔(新月)
満潮 時刻04:52 潮位133
満潮 時刻14:09 潮位149
干潮 時刻09:10 潮位110
干潮 時刻21:50 潮位-6
人工的なのがわかる
少し離れた所から見たトーチカ。上が陥没している。
潮位119近い時の波
干潮だと岩場をぐるっと回り込むことができるほどに波が引くようだ
興津海岸を一望できる高台
普通の住宅地もありながら、この世の果てのような気分も味わえる
小さな祠と鳥居がある
地形図に路傍祠の記号もない
名前がわからない
気持ちのいい高台だ
中央の台形的な岩礁が興津海岸トーチカの場所
大きな漁港ではないが、海産物収穫のための漁業設備があり、近くの小屋に出入りして作業している人たちがいた。
はまなすが群生している
プチトマトのような実がなっていた
望洋湯(ぼうようゆ) _ 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合
住所 〒085-0813 釧路市春採6丁目4-5
TEL 0154-42-6522
+81 154-42-6522
営業時間 12:00〜23:00
駐車場 有
定休日 木曜日
お店からのPR 創業:昭和34年 2代目
入浴料480円
サウナ追加料金なしで入れるのが嬉しい
富士溶岩露天風呂あり
内湯は3つの湯船
普通のジェットバス(湯温は熱め)
オレンジ色の湯
薬湯ふくじゅこう
フロント式 フロント前に休憩所あり
休憩所の写真撮らせてもらった
わりとお客さん多い
地元の常連客の人達っぽい
昭和後期か平成初期頃の築に見える。
八王子南バイパス延伸工事(3工区)
「一夜で架ける」R2国道20号八王子南BP館高架橋上部その6工事 パンフレットを配布していたのでもらってきた。
【夜に架ける】多軸式特殊台車による一括架設(国道20号八王子南バイパス館高架橋)
架橋工事は6月28日23:05~6月29日05:00に一夜で行われた。






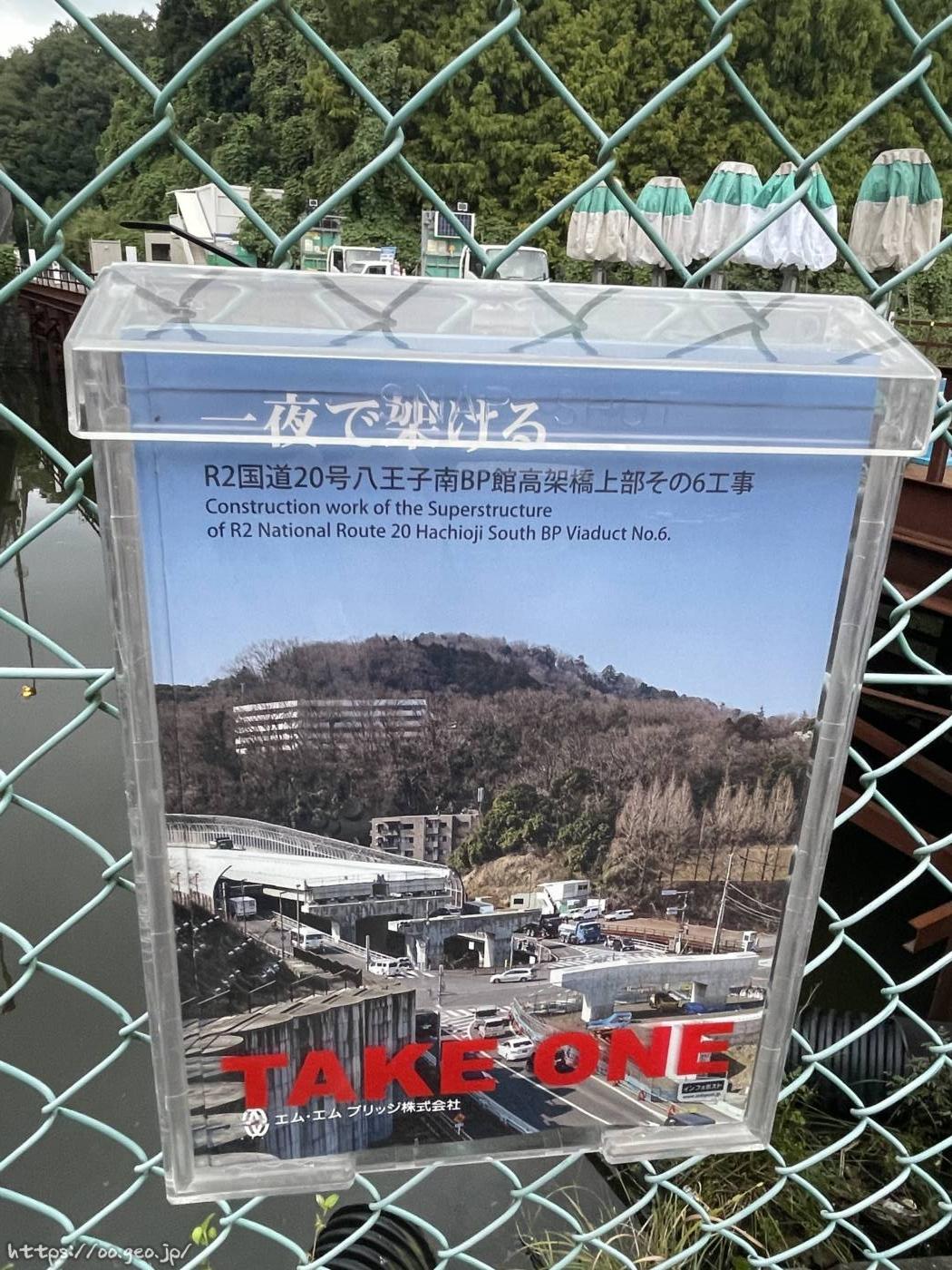
【夜に架ける】多軸式特殊台車による一括架設(国道20号八王子南バイパス館高架橋)
架橋工事は6月28日23:05~6月29日05:00に一夜で行われた。
【夜に架ける】多軸式特殊台車による一括架設(国道20号八王子南バイパス館高架橋) 架橋工事は6月28日23:05~6月29日05:00に一夜で行われた。 
参考:八王子南バイパス _ 相武国道事務所 _ 国土交通省 関東地方整備局
林の中にある公園で、夏は木陰が涼し気で良い。虫も多そう。貯水池のような池がある。
〒193-0944 東京都八王子市館町1301-3
ごりょうじんじゃ
〒193-0944 東京都八王子市館町1271
超望遠レンズのカメラマンがたくさん屯していて、何事かと思ったらアオバズクの観察隊だった。林に同化していて、人から教えてもらわないとどこにいるかまったくわからなかった。今日あたり巣立つんじゃないかとのお話で、何とか頑張って960mmの超望遠コンデジで手持ち撮影してみたが、これが精一杯。日中はほとんど身じろぎもせず枝に止まったままだったが、18:50過ぎあたりから活発に活動し始めたが、暗くなりすぎて肉眼でもカメラでもよく見えなくなってしまったので、巣立ちを確認する前に退散した(ずっと上ばかり見上げていたら首が痛くてたまらなくなったし)。野鳥撮影に三脚は必須だな…
もう1羽のアオバズクの雛。保護色で完全に幹に同化している…夕闇での960mm超望遠コンデジ手持ち撮影では、これが精一杯。
解体間近の大橋眼科医院。1980年代竣工とのことだが、まるで大正時代か昭和前期の建物のようによくできている。
〒120-0034 東京都足立区千住3丁目14
同じく北千住にある菅田眼科。こちらもそこまで古くはないんだろうが、レトロに見える。
〒120-0034 東京都足立区千住2丁目6-1
芳味(ほうみい) HOME-Y。 居酒屋かと思ったら食堂だった。壁一面に新聞紙を貼り付けた外装が、錆びたトタンに見える。向かい側の店舗は廃屋。店の半分を覆う蔦は脇の路地まで伸びている。向かいの墓地(浄土宗 三宮神山 勝専寺の墓地?)の煉瓦塀は古そうに見えたが、よく見るとレンガは新しめだった。
〒120-0034 東京都足立区千住2丁目31-2
北千住駅前通り商店街の婦人用衣料品店・小杉屋。レトロだ…
〒120-0034 東京都足立区千住2丁目
北千住の無料PCR検査場は普通の民家のようだ。生活感がある…
アクセスチケット 北千住店の自販機で都内共通の銭湯回数券を購入。450円。最後の1枚だった。ついでにマクドナルドのハンバーガー券も買ったが、自販機がイカれかかっているようで、チケットが出てこないトラブルに見舞われた。よくあることなのか、レジの人に言ったらさほど驚いた様子もなく代わりのハンバーガー券を手渡しされた…
〒120-0034 東京都足立区千住2丁目24−3
https://www.access-ticket.com/shop/detail/29
ベランダが木造りの木造アパートがある。
金券ショップチケッティ 北千住東口店。青春18きっぷを売っていたので買おうと思ったが、現金の持ち合わせがなくて買えなかった…クレジットカードなどではダメだそうだ。
〒120-0026 東京都足立区千住旭町3-8
梅の湯方面に行く途中、門柱だけやけに立派な廃屋があった。
北千住の東口近くにある銭湯・旭町梅乃湯(梅の湯)入浴。昔ながらの破風造りの銭湯。コインランドリー併設。昭和30年築らしい。フロントでおかみさんに銭湯スタンプを1個押してもらった。前回のスタンプの日付を見たら2年前だった。都区内の銭湯で入浴するのはおよそ2年ぶりということになるかと思うが、広い浴室と浴槽で入浴するのはやっぱり気持ちいいな。
〒120-0026 東京都足立区千住旭町41-11
入店してから銭湯セットを忘れてしまったのに気づき、ボディタオルを400円で購入。体を拭くタオルを1枚無料で貸し出ししていたので助かった。シャンプーとボディーソープも浴室に設置してあった。浴室は白基調の壁で、浴槽は2つある。岩盤泉と?鉱泉だったかな。ペンキ絵は、公式サイトに掲載されている写真とは違う絵柄で、「2020.6.7 ナカジマ」のサイン入りのペンキ絵あり。湖畔と山の風景。男湯は富士山。女湯は低山。黄色い風呂桶はあったがケロリン等の広告はなし。脱衣所も昔ながらの木造りの高天井。脱衣所の中央にロッカーあり。ハンドドライヤー&マッサージ椅子あり。ロッカーの上には観葉植物の鉢が3つほど。
都内の銭湯料金、アクセスチケットの自販機だと480円が正規料金のように書いてあったが、500円に値上げされたのか…。
北千住の東京メトロ全駅スタンプラリー駅スタンプポスター。本物のスタンプは作ってないのかな。
千代田線の国会議事堂前駅。
とつぜん膀胱炎になってしまい、あわてて病院へ。
いきなりの血尿にびっくり。癌かなにか!?と恐怖で真っ青になったよ?
調べて見ると、膀胱炎はわりと日常的な病気で普通にかかってる人も多い。
命にかかわる大病ではなくて(今のところ)良かった…(良くないけど)
病院行く途中に久しぶりに高尾バッティングスタジアムに寄ってみる。2020年9月に閉業してしまったバッティングセンターだけど、まだ解体されていない姿を見て安心する。
高尾バッティングスタジアム前の上館バス停は草ぼうぼう。
バッティングスタジアムの入口も草ぼうぼう。
バッティングスタジアムと書かれた黄色いビールケースは無くなってたな〜。
入口は以前と変わりなく。
「本日 休業」の張り紙もそのまま。
いや、そのままじゃない。
よく見るとうっすらと鉛筆で寄せ書きが。
なにこれ。こんなん泣かせるやん
・゜・(つД`)・゜・
隙間から見えるゲーム機(?)は当時のままだった。
裏側のこのボロさがいい
ツタのからんだネットもそのままだったけど、裏側にあった廃車はなくなってたみたいだった。雑草に隠れてただけかもしれないけど。
藪の生い茂った小道を通り抜けると
長沢園という園芸屋に出る。
現在は営業しているのかわからない園芸屋さんだが、そこの敷地に生える巨大な金木犀の木がカットされていた。高枝が道路に覆いかぶさるようにして生えていたが、個人的にはその風情が昔道って感じで好きだった。
長沢園
〒193-0944 東京都八王子市館町625
0426616713
https://goo.gl/maps/YwyU2QD4B2aDimcu9
長沢園 – 日本盆栽協同組合東京支部
多摩酪農農業協同組合 横山第一集乳所の古い建物
医療センターに向かう小道、昔は未舗装だった細い歩道のわきに石柱がたつ。現在は民家の敷地内にあるが、古くから伝わる道の1つだったのでないかと思う。
見ていたら猫がにゃーんと鳴きながらついてきた。
痩せっぽちだが、とても可愛らしい鳴き声の猫だった。
医療センター前の八王子南バイパス工事現場に出ると三叉路の法面工事が終わっている。
医療センターにはDMATの救急車が。
東京医科大学八王子医療センターの裏側にある液化窒素タンクやガスタービン発電施設など。
放射線管理区域
スプリンクラー送水口のわき(何の変哲もない場所)に避雷設備があった。
避雷設備接地極埋設標
高さ20mというと一般的なビルでは大体7階建てに相当するらしい。医療センターは屋上ヘリポートを入れて7階建て。メインの建物は4階建て~5階建て。
館ヶ丘団地の基準点(ココ)。でも地形図などを見てもわからない。
医療センター前には明確に185m地点が存在するのに。
以下、館ヶ丘団地や医療センター周辺のマンホール。
最近作られたデザイン性が高いマンホールにはあまり惹かれない方なので、そういうのは写真撮ってない。
ひたすら茶色い古くて無骨なマンホールばかり写真を撮る。
ビッグ・エーには立ち寄らず…
ビッグ・エーのこの棟番号すき。
病院で検査してもらって薬を処方してもらったので、狭間駅方面へ移動。
途中、北野街道からイトーヨーカドーの方に抜ける小道にある石標(ココ)。
残念ながら上が折れてしまっていて判読不可能。
ただ「○○方面ニ至ル」「○○支部建之」という文字から、結構古いものでないかと思われる。
昔はこの道も舗装されておらず、古道らしく奇妙に曲りくねった風情が良かった。
便宜上仕方ないとは言えど、何でもかんでもアスファルトで埋めてしまうのが好きではない…
近くの完山金属に飾ってある鉄道車輪と南武線の古い時刻表は年々錆びていく。
狭間駅近くのラーメン黙古寿の隣にあったカラオケ居酒屋「杏」がいつのまにか解体されて更地になっていた。ラーメン黙古寿も以前は21時まで営業していたのが、2020年1月15日から17時までの営業に変わってしまった。コロナが関係しているのかどうかは分からない。ここの店内、こけしがたくさん飾ってあるので、こけしが好きな人にもおすすめ。